「口内炎が頻繁にできて困っている」という方は実は少なくありません。痛みを伴い、食事やお手入れが難しくなるケースも多い傾向にあります。歯並びや噛み合わせの崩れも口内炎のできやすさには大きく関係しているので、心当たりのある方は放置せずに一度歯科医院へ相談してみるといいでしょう。こちらのページでは、歯並びと口内炎の関係や予防するポイントなどについて分かりやすくまとめました。お悩みの方はぜひご参考ください。
目次
歯科矯正で歯並びを整えると口内炎ができにくくなる

歯並びや噛み合わせは口内炎と深いつながりがあり、改善することでできにくくなったケースは少なくありません。口内炎は基本的に1~2週間程度で治るトラブルですが、痛みが強い間は食事やお手入れが困難になりやすく、ストレスも増加する傾向にあるため注意が必要です。口内炎ができにくいお口に改善することは、身体的はもちろん精神的にもメリットは大きいといえます。お悩みの方はまずお口の環境を見直してみましょう。
口内炎の種類は5つ!それぞれの特徴について知ろう

口内炎は5つのタイプに分けられ、それぞれ原因や特徴が異なります。とくに原因は知っておくことで予防がしやすくなるのでおすすめです。現在口内炎がある方は鏡で見た目を確認してから以下の内容を読むとタイプが分かりやすいでしょう。
アフタ性口内炎
白っぽく境界線がはっきりとしており、浅い見た目が特徴です。もっともできやすいタイプで、主な原因として「免疫力の低下」「ストレス」「栄養不足」などが挙げられ「全身性疾患の症状」で出現するケースも少なくありません。繰り返してできる場合は「再発性アフタ性口内炎」に名称が変わります。
外傷性口内炎(カタル性口内炎)
外部からの刺激によってできた口内炎を指し、水ぶくれやヒビ割れのような症状が現れるのが特徴です。主な原因として「虫歯」「入れ歯の不具合」「口腔粘膜の損傷」「やけど」「薬品の刺激」
などが挙げられます。
ヘルペス性口内炎
複数の水疱ができるのが特徴で、乳幼児に多くみられます。激しい痛みや発熱を伴いやすく、口内炎のなかでも症状が重い傾向にあるため注意しなくてはいけません。主な原因として「単純ヘルペスウイルス」「性感染症」が挙げられます。
カンジダ性口内炎
白いこけ上の斑点が特徴で、多くの場合痛みはほとんどありません。しかし、症状が変化して痛みやしびれ、味覚異常を感じるケースもみられます。主な原因として「口腔内のカンジダ菌(カビ)の過剰増殖」が挙げられます。
ニコチン性口内炎
白斑や赤い発疹ができるのが特徴で、粘膜や舌が厚く硬くなるケースがほとんどです。主な原因として「喫煙習慣」が挙げられます。
歯並びの崩れが原因で発生する口内炎はどのタイプ?
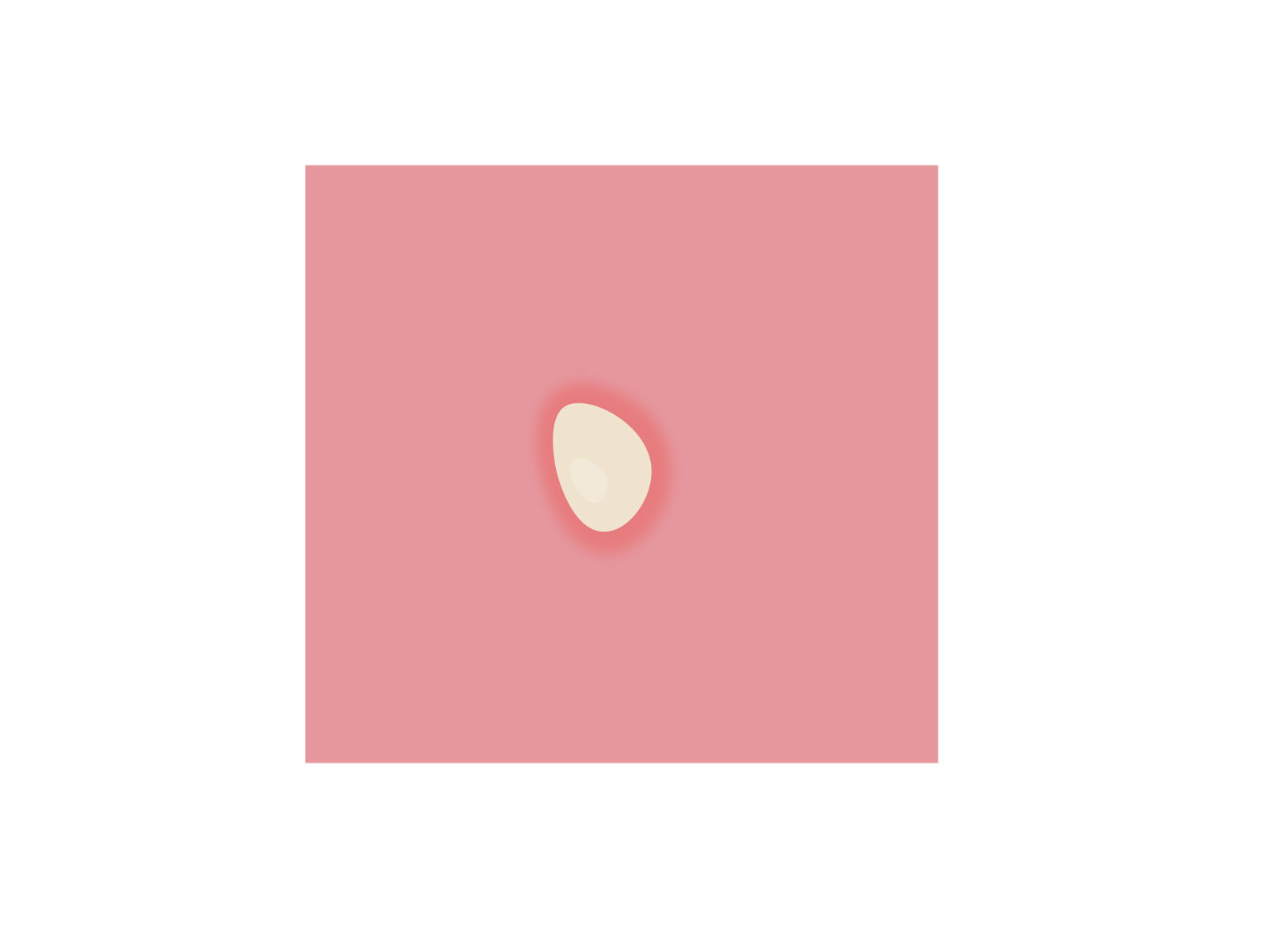
歯並びの崩れが原因で発生する口内炎は「アフタ性口内炎」と「外傷性口内炎(カタル性口内炎)」が多い傾向にあります。理由を正しく理解して予防に役立てましょう。
食べ物をしっかり噛みつぶせない
歯並びや噛み合わせが崩れていることで噛む部位に偏りがあったり、口周りの筋肉の負担の偏りや顎関節への負担増加によって咀嚼回数が減っていたりすると、食べ物を固形の状態で飲み込みやすくなります。しっかり噛んですり潰された状態にくらべて栄養が吸収されにくく、その結果アフタ性口内炎の発生につながるケースが少なくありません。歯並びの問題に加えて早食いの癖がある方はとくに注意が必要です。
粘膜を巻き込んで噛んでしまいやすい
歯並びや噛み合わせが崩れていると、食べ物を噛むときに粘膜を巻き込んで噛むというトラブルが起こりやすくなります。とくに歯列がデコボコしている叢生はその可能性が高く、外傷性の口内炎が同じ部位にばかりできるケースも珍しくありません。長期的に同じ部位に外部的刺激があると、組織が硬くなり癌化するリスクもあるため注意が必要です。
矯正治療中も口内炎ができやすい!?予防するポイント

歯科矯正を始めると初めての場合多くは痛みが気になりませんか?口内炎による痛みや歯が動く痛みがあります。その痛みがどうしても耐えられない場合は矯正治療をして歯並びが整うと口内炎はできにくくなりますが、治療中はさまざまな理由から口内炎ができやすくなる傾向にあります。とくに治療を始めたばかりの頃は痛みや装置の感覚に慣れていないためリスクが高めです。予防するポイントをしっかり抑えてモチベーションの維持に役立てましょう。
栄養のバランスを意識した食事を心がける
矯正治療が始まって歯が動く痛みで食生活が変化する方は少なくありません。偏った食事を続けていると、免疫力の低下や栄養不足が原因でアフタ性口内炎ができてしまうことがあるため注意が必要です。痛みが強いときは無理に硬めのものを食べる必要はありませんが、痛みが落ち着いている間も同じような食生活だと栄養が偏ってしまいます。痛みが少ないときは栄養バランスがいい食事を意識して摂るようにしましょう。
装置と粘膜のあたりが強い部位に専用のワックスを使う
ワイヤー矯正の装置が粘膜に強くあたり続けていると、外傷性の口内炎ができることがあります。とくに治療を始めたばかりの頃は、粘膜が装置の感覚に慣れていないため口内炎ができるリスクは高めです。専用のワックスで装置を覆うことで粘膜へのあたりを弱められるので、心配な方は早めに歯科医院へ相談して受け取っておきましょう。
お口の中を清潔に保つ
矯正治療中は装置があることでお手入れが難しくなります。とくに固定式のワイヤー矯正は、通常の歯ブラシのみでは不十分であり、一歯用のコンパクトブラシを使用したり、フロス
をワイヤーをくぐらせてから使うなどの工夫が必要です。お手入れに時間はかかりますが、お口の中が不衛生だと口内炎ができやすく、その治りも悪くなるので丁寧に管理しましょう。お口の中を清潔に保つことは、虫歯や歯周病予防だけでなく、口内炎による痛みや不快感の減少にも効果的です。
装置の種類によって口内炎のできやすさは異なる

矯正治療で使用する装置は、粘膜へのあたり具合や口内炎ができやすい部位がそれぞれ異なります。治療中の口内炎ができるリスクは一時的なものではありますが、ある程度歯並びが整うまでは繰り返す可能性があるため、注意しなくてはいけません。装置の特徴を理解しておくことで快適な治療につながりやすくなるでしょう。
ワイヤー矯正(表側矯正)
歯の表面にブラケットとよばれる装置を貼り付けて、そこにワイヤーをとおして歯並びを整える方法です。装置が1本1本の歯につくため微調整がしやすく、幅広い症例に対応できます。装置が固定式である程度厚みがあり、感覚に慣れるのに時間がかかる人も少なくありません。唇や頬の粘膜に口内炎ができやすい傾向にあります。
裏側矯正(舌側矯正)
ワイヤー矯正の一種で、歯の裏面に装置を貼り付けて行う方法です。ワイヤー矯正の強みを活かせるだけでなく、正面から装置が見えないため「目立ちにくい治療法」をご希望の方にもおすすめできます。装置は表側矯正と同じく固定式である程度の厚みがあります。慣れるまでは舌に口内炎ができやすく、発音や滑舌に支障をきたすケースも珍しくありません。
マウスピース型矯正
マウスピース型の装置を定期的に交換して歯並びを整える方法です。装置が薄く、取り外しが可能なため、ワイヤー矯正にくらべて装置が原因の口内炎はできにくいといえます。しかし、固定式でない分患者様の自己管理レベルによって仕上がりに差がでやすいので「装置のつけ忘れ」や「装着時間の不足」には十分注意が必要です。
【梅田キュア矯正歯科のマウスピース矯正について詳しくはこちら】
歯科矯正で口内炎ができにくいお口を目指そう
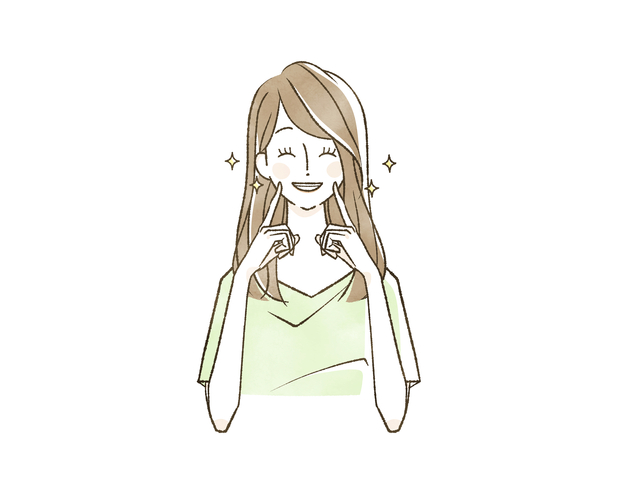
歯並びや噛み合わせが崩れていると、粘膜を巻き込んで噛んで外傷性の口内炎ができたり、しっかり噛めないことで食べ物の栄養の吸収が悪くなり、アフタ性口内炎につながる可能性があります。矯正治療中は口内炎ができるリスクが少し高まりますが、治療を終えるころには以前とのちがいにきっと驚くことでしょう。「できるだけ口内炎のリスクが少ない自分に合った装置で治療をしたい」という方も、まずは一度当院までご相談ください。

