前歯は口元の印象に大きく関係してくるため、歯並びが悪いと審美的なコンプレックスになりやすい部分です。出っ歯や凸凹の歯並びで口元を隠しながら話しをする習慣になっている方もいます。審美的な問題だけでなく、噛み合わせのバランスも崩れていることが多いため、改善した方が良い状態です。そこで今回は、前歯の歯並びが悪くなる原因とその改善方法について詳しくご紹介します。
目次
前歯の歯並びが悪くなる7つの原因
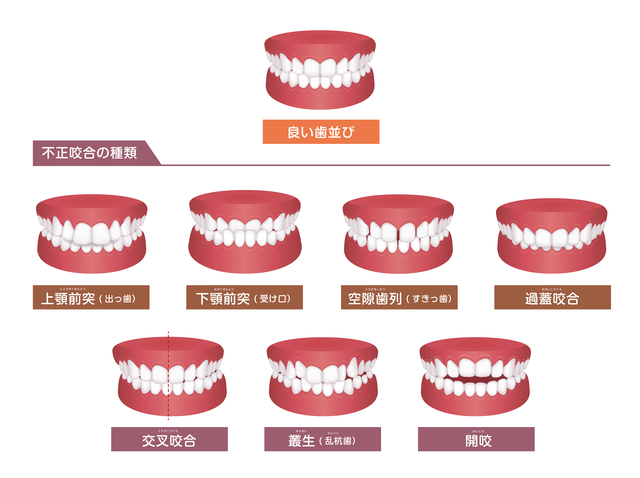
前歯の歯並びが悪くなる原因は様々なものがありますので、ご紹介します。
1 顎のスペース不足
顎のスペースが足りないと、歯が並ぶ場所が少なくなってしまうため、前歯の歯並びが悪くなる要因になります。顎の発達はお子様の時期に急速に発達しますが、この時期にやわらかい物を食べる習慣がついていると、顎の正しい発達が促されません。食生活の変化で、ファストフードやインスタント食品も手軽に取り入れられるようになりました。ただし、しっかり噛むことで顎の発達が促されますが、あまり噛まずに食べることができる食事ばかりしていると、顎が小さく、スペースが足りない状態になる場合があります。歯ごたえのある食品も取り入れ、1口30回程度しっかり噛む習慣をつけましょう。
2 骨格的な問題
前歯の歯並びの悪さの原因の1つとして考えられるのは、顎が小さい、上下の顎のバランスが悪いなどの骨格的な問題です。これは、遺伝的な要因が強く、生まれつきの骨格が関係していることが多いでしょう。骨格のアンバランスさに問題がある場合には、お子様の時期に骨格のバランスを整えながら、永久歯が正しい位置に生えてくるように促す治療があります。大人になってから治療が必要なケースでは、骨格のアンバランスを手術して矯正治療をする外科矯正が必要なケースもあります。お子様の時期に、矯正治療をすることで、審美的にも機能的にも良い状態で大切な歯を守ることにもつながります。
3 永久歯に生え変わる時期よりかなり早く乳歯を失ってしまった
外傷や虫歯などで、早期に乳歯を失ってしまった場合には、そのスペースを埋めようと隣の歯が少しずつ動いてきます。そうすると、歯が生えるスペースが足りず、歯列からはみ出て生えてくる可能性があります。また、乳歯には、永久歯が正しい位置に生えてくるようにガイドをする役割もありますが、その働きもないため、歯並びが悪くなることがあります。
4 歯周病が進行している
歯周病は自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行していることが多い疾患です。初期の症状は歯ぐきの腫れや歯磨きの時の出血などですが、進行すると歯を支えている骨を溶かしてしまいます。そうすると、歯がグラグラして、抜け落ちてしまうこともあります。歯が安定していないと、左右の歯も少しずつ動いてしまい、歯並びの悪影響を及ぼすことがあります。
5 親知らずが歯を押している
親知らずは、20歳前後に生えてくることが多い歯で、全く生えない方もいます。また、永久歯の最後に生えてくる歯のため、歯が生えるスペースが足りずに斜めに生えたり、真横に生えてしまったりすることもあります。そうすると、手前の歯を押して歯並びが悪くなることがあります。大人になってから少しずつ歯並びが悪くなってきた方は、親知らずが影響している場合もあります。
6 口呼吸
呼吸をする時は、鼻で呼吸をする鼻呼吸が正しいのですが、口が閉じにくいなどの原因で口呼吸になってしまうことがあります。口呼吸が習慣化すると、口をぽかんと開けていることが多く、唇や頬からの正しい圧がかかりません。そうすると、前歯が少しずつ出てしまい、歯並びが悪くなる原因になります。そのほかにも口呼吸はデメリットがあり、細菌やウイルスをダイレクトに吸い込んでしまうため、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。鼻の疾患が影響していることもあるため、鼻炎などの症状がある方は耳鼻科に相談しましょう。出っ歯などが原因で口が閉じにくい場合もありますので、その場合には、矯正治療が必要です。
7 加齢による口周りに筋力の低下
年齢を重ねると、皮膚のたるみや口周りに筋力が低下して、歯にかかる圧が弱くなります。唇や頬からの正しい圧がかからなくなってしまうと、歯が前に出てしまうことがあり、前歯の歯並びの悪さにつながる場合があります。
前歯の歯並びの悪さが原因で起きること

・審美的にコンプレックスを抱きやすい
前歯の歯並びが悪く、斜めになっていたり、凸凹していたりするとコンプレックスを抱きやすくなります。歯並びは、左右対称になっていて、全体的な噛み合わせのバランスも整っていることが大切です。歯並びが悪い部分は、外見的な問題にもつながりやすく、特に思春期の時期などに意識することが多く、早めに改善した方が良い状態です。
・虫歯や歯周病のリスクが高くなる
前歯の歯並びが悪いと、重なっている部分や凸凹している部分に汚れが残りやすくなります。その部分は歯ブラシも当たりにくくなってしまうため、虫歯や歯周病のリスクが高くなります。また、汚れが残りやすいことから口臭の原因にもなってしまうため、周囲の方に悪影響を及ぼしてしまうこともあります。
・噛み合わせのバランスが崩れる
前歯が歯列にきちんと並んでおらず、凸凹していると、噛んでいない部分があり、奥歯に負担がかかりやすくなります。また、強く当たっている部分の歯や顎には負担がかかりやすく、歯の寿命を縮めてしまったり、顎関節症になったりする場合もあります。
前歯の歯並びを改善する方法
前歯の歯並びが悪い場合には、自然に整うことはほとんどないため、矯正治療が必要です。
ワイヤー矯正
ワイヤー矯正は、ブラケットとワイヤーを用いて歯並びを改善する方法です。
・表側矯正

表側矯正は、歯の表側に矯正装置をつける方法で、歴史があります。大幅に歯を動かす症例にも対応しており、歯並びの不正が強い方の多くが適用になります。矯正装置をつけた時に厚みが出てしまうことがありますが、従来の金属の矯正装置だけでなく、白や透明のブラケットも選択できるようになり、装置の見た目の負担が軽減されます。
・裏側矯正(舌側矯正)

裏側矯正(舌側矯正)は、歯の裏側に装置をつけるため、矯正中の装置の見た目がほとんど分からない矯正方法です。矯正装置の見た目が気になって、矯正治療を迷っている方におすすめの方法です。歯科医師の技術力や経験が必要な矯正治療ですが、当院では数多くの裏側矯正(舌側矯正)を行っていますので、お気軽にご相談ください。
・マウスピース型矯正

マウスピース型矯正は、お口の中をスキャンして透明のマウスピースを作製し、少しずつ形の違うマウスピースに交換しながら歯並びを整える方法です。取り外しができる方法のため、食事や歯磨きを矯正前と同様に行うことができます。ただし、1日20~22時間の装着が必要なため、自己管理が必要な方法です。決められた装着時間より短くなってしまうと、治療計画通りに歯が動かない可能性があります。
【梅田キュア矯正歯科の矯正装置について詳しくはこちらをクリック!】
【まとめ】

前歯の歯並びが悪くなる原因は、遺伝的な要因だけでなく、歯周病や口呼吸など後天的な原因が関係している場合もあります。そのため、子供のころからだけでなく、大人になってから歯並びが変化する場合もあります。前歯の歯並びが悪い場合には、矯正治療で改善しましょう。当院は、表側矯正、裏側矯正(舌側矯正)、マウスピース型矯正に対応していますので、患者様のお口の状況とご希望に合わせてより良い矯正方法をご提案いたします。

